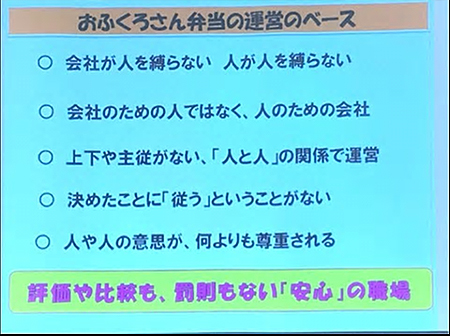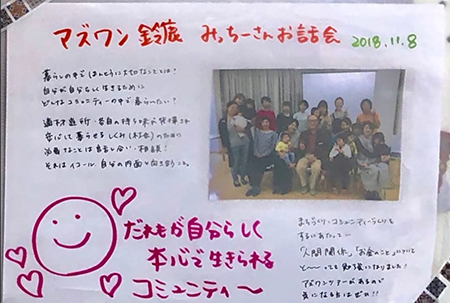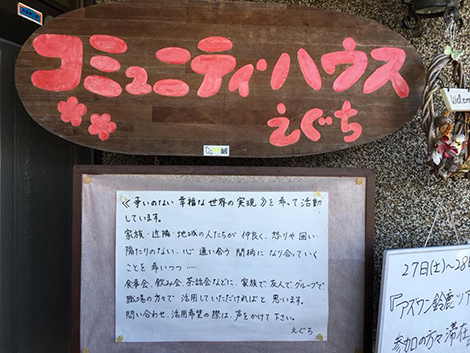「やらせる」「やめさせる」がない子育ての試み その2
子育て中のお母さん! 前回このブログで、「やらせる」「やめさせる」がない、アズワンコミュニティでの子育てについて紹介しました。「え!?それってどういうこと?」と、いろいろ疑問があったかと思います。今回はその続き。そんな子育てをやってみようとしているコミュニティで暮らすお母さんにインタビューしてみました。(取材:いわた)

1歳の男の子のお母さん、岸上舞子さんの話
舞子さんは、3年前(2015年)に福岡から留学生として鈴鹿コミュニティにやって来ました。その後、岸上拓也さんと結婚し男の子を出産。現在1歳になるさくと君と家族3人で暮らしています。
子どもは、自主保育の場、「キンダーハウス・チェリッシュ」で過ごし、他のお母さんたちやサポートに入ってくれる周りの人たちに見守られながら、すくすくと育っています。

写真はさくと君(左)とたつみ君
舞子さんは、「サイエンズスクール」のコースに参加したり、日常ではサイエンズ研究所が主催する「サイエンズサロン」㊟1に参加するなどして、自分の内面に関心を向け、自分の気持ちや考え方がどんなふうに態度や行為に現れるのか、自分とも向き合いながら、子どもに接しているようです。
最近の「サロン」で話題になったのが、人に「やらせる」「やめさせる」というテーマでした。人を強制して人を動かそうとすることが、そもそも争いの原因ではないか、というあたりです。子どもに対しても、大人は強く出て子どもを動かそうとしますが、それは、精神的な苦痛を与えてことであり、人に対して警戒心を植え付けているのかもしれません。
では、本来の人と人、親と子の間柄とはどういうものでしょうか、そして、人に対してどんな働きかけが、人間らしさ、子どもらしさ、その人らしさが発揮できるのでしょう。今、コミュニティでは暮らしの中で、そんなところを明らかにしながらやってみようとしています。そんな暮らしの中にいる舞子さんです。
◆絵本を切った話
――子どもに「やらせる」「やめさる」ってことは日常的にありそうだけど、どうですか?
舞子 チェリッシュにいたときこんなことがあった。4歳の男の子が絵本を持っていて「ハサミをちょうだい」って私のところに来たので、渡したの。そしたら、絵本をザクザクって切った。
私はすぐ反応が出た。「やめてほしい」「大事にしてほしい」「切らないでほしい」って思った。
一緒にいた人が「やめてほしい、本は切らないでほしい」って声をかけたんだけどね。そしたらその子、「やーだー」って言って、もう1ページ切った。そして隣の部屋に走って行った。
その時のことを「サロン」で振り返った。
自分には、「本は切っちゃダメ」「大事にするもの」、そういう「考え」がすごくあるなって思った。だから見た瞬間に「止めてほしい」って思うんだけど。でも、それが本当に自分の願っていることから出てきているのかなって?考えた。
――ん? どういうこと? 本は切ったらダメ、じゃないの? だから、切ってほしくないって思うよね?
舞子 そういうのが、「本は大事にするもの」「切ってはいけないもの」っていう自分の中にある「考え」の方から出てきているのかなって。
――「考え」の方、っていうと、つまり、「教えられたこと」っていうことかな…?
舞子 そう。だから、そういう「考え」から来ているとしたら、それって自分の意志って言えるんだろうかって思ったの…。
そのときの自分の気持ちは? とか、本当に自分はどうしたかったのかな?って。そういうのがありそう。
――なるほどね。「教えられた考え」ではなくって、その時の自分の気持ちが何かあるんじゃないかと。
舞子 その子は、「ハサミちょうだい」って言うときには、すでに本を持ってたんだよね。その子は何かしようとしてたことがあるのかな? そこを知りたいなって思った。
――そうか、子どもの方には、「切ってはいけない」ってないんだろね。大人には、それを教えないといけないっていう「考え」があるね。
相手の意志や気持ちに働きかける
舞子 サロンで検討してたときに、「やらせる」「やめさせる」って、本来出来ないんじゃないか、それってどういうことなのかなって考えた。
そして、相手の意志とか、気持ちに働きかけるって、本に書いてあって、それってどういうことだろう? って考えた。相手の意志に働きかけるんだったら、働きかける自分も、自分の意志とか気持ちで働きかけないと伝わらないんじゃないかな、って思った。それは、そうかもなって。
そういうことが、子どもたちが人間らしく育っていくことに関係してくるのかな…って思う。
――最近は、どんなふうに子どもと接しているの?
舞子 なんか、「やろう、やろう」ってしていた感じがあった。自分の中では、これをやりたいって、あんまり出てこなくって。
円ちゃん(チェリッシュで一緒のお母さん)からは、子どもたちと「あれやってみたいんだよね」っていう話を聞くと、私は、そういうふうに出てくるのが、「いい」みたいに思ってたのかな。
最近は、子どもたちが、「これしてほしい」とか言ったときに、自分がやろうと思ったらやるって感じかな。
あまり自分からこれしてみたいな、って出てきたらやったりするけど、無理にこれやろうって思ってた時は結構きつかった。
子どもたちが退屈しないように、集中出来る遊びを考えるとか、そういうのが「いい」って思ってた。
――子どもたちって、退屈するのかな?
舞子 どうなんだろうね?
子どもが、「面白くない」とか、「家に帰りたいとか」、そういうのを聞くと、退屈なのかなって思うんだけど。そう言った瞬間から、次の遊びが始まってたり、帰りたいっていってたのが、しばらく遊んだりとかするから、そのときそう思ったことを言ってるんだろうな。
――子どもに退屈させないように遊びを与えようとする「考え」があるよね。
舞子 集中して出来ることは、それはいいなって思うけど、そういうことが子どもの満足みたいに思ってた時期もある。だらだらして見える時でも、ただ一緒に過ごしているという時でも、いいのかなって今は思う。
――そういう時でもお母さんが安心してみてられたら、いいんだろうね。親の方が、心配しちゃって、手を出したくなったりするのかな。子どもの様子は気になるよね。
他のお母さんたちの目線があって
舞子 他の子の様子を聞いたりすると、やっぱり気になるかな。「今日はつむちゃん漢字を書いてたよ」とか、LINEで写真を送ってきたりしてね。さくとはまだその年代ではないけど。他の子をちょっと遅れてるって感じたりとか。
何か比べて、そっちの方が「いい」みたいに思ったり、同じように出来るのが「いい」って思ったり。
たつみ君とさくととは1か月ちがいで、歩くのはさくとの方が早かったんだけど。たつみ君は器用に物を入れたりしているのみると、さくとにもそういうのさせてもらえてるのかなって見たり…。さくと君は、外に出て走り回ったりするのがどうも楽しそうだよ、とか、そんなふうに見てもらってたり…。
私から見ると、たつみ君がすごく穏やかに見えるんだよね。そういうのが羨ましくなったりする、さくとは乱暴に思ったり。たつみ君はおとなしくて素直みたいに受け取ってたり。
そういう話を、知美さんとか純奈さんとか、月に1回ミーティングしてて、そういう時、話してる。
でも、「さくとすごく楽しみだよね。大きくなってくのが」って、「なんにでも関心があるし、やろうとする関心があるし」って。そういうのを聞いて、へーって思ったり。

インタビューを終えて。
子どもを見守る目線がいろいろあって、自分から見ているのと違った視点で見てくれていることが、お母さんにとっても安心なのかなと思いました。取材中、さくと君は、お母さんと一緒にいましたが、くっついたり、離れたり、部屋にあるおもちゃで遊んだり、おっぱいを飲みに来たり、満足すると、離れて、おもちゃで遊んだり、と。そんな子どもの気持ちにそって舞子さんも対応していて、それが自然に感じました。子どもの欲求って、その時々でどんどん変わっていくし、それを見てお母さんも反応してるのかな、と。
㊟1「サイエンズサロン」――人と社会の本質を探るサイエンズ研究所が主催する探究の機会。参加対象は、サイエンズ研究所会員。毎週1回2時間で6か月間行われる。人や社会の本質に通じるテーマを探究しながら日常生活への顕現を試みる。
【 続 き を 閉 じ る 】
最近の「サロン」で話題になったのが、人に「やらせる」「やめさせる」というテーマでした。人を強制して人を動かそうとすることが、そもそも争いの原因ではないか、というあたりです。子どもに対しても、大人は強く出て子どもを動かそうとしますが、それは、精神的な苦痛を与えてことであり、人に対して警戒心を植え付けているのかもしれません。
では、本来の人と人、親と子の間柄とはどういうものでしょうか、そして、人に対してどんな働きかけが、人間らしさ、子どもらしさ、その人らしさが発揮できるのでしょう。今、コミュニティでは暮らしの中で、そんなところを明らかにしながらやってみようとしています。そんな暮らしの中にいる舞子さんです。
◆絵本を切った話
――子どもに「やらせる」「やめさる」ってことは日常的にありそうだけど、どうですか?
舞子 チェリッシュにいたときこんなことがあった。4歳の男の子が絵本を持っていて「ハサミをちょうだい」って私のところに来たので、渡したの。そしたら、絵本をザクザクって切った。
私はすぐ反応が出た。「やめてほしい」「大事にしてほしい」「切らないでほしい」って思った。
一緒にいた人が「やめてほしい、本は切らないでほしい」って声をかけたんだけどね。そしたらその子、「やーだー」って言って、もう1ページ切った。そして隣の部屋に走って行った。
その時のことを「サロン」で振り返った。
自分には、「本は切っちゃダメ」「大事にするもの」、そういう「考え」がすごくあるなって思った。だから見た瞬間に「止めてほしい」って思うんだけど。でも、それが本当に自分の願っていることから出てきているのかなって?考えた。
――ん? どういうこと? 本は切ったらダメ、じゃないの? だから、切ってほしくないって思うよね?
舞子 そういうのが、「本は大事にするもの」「切ってはいけないもの」っていう自分の中にある「考え」の方から出てきているのかなって。
――「考え」の方、っていうと、つまり、「教えられたこと」っていうことかな…?
舞子 そう。だから、そういう「考え」から来ているとしたら、それって自分の意志って言えるんだろうかって思ったの…。
そのときの自分の気持ちは? とか、本当に自分はどうしたかったのかな?って。そういうのがありそう。
――なるほどね。「教えられた考え」ではなくって、その時の自分の気持ちが何かあるんじゃないかと。
舞子 その子は、「ハサミちょうだい」って言うときには、すでに本を持ってたんだよね。その子は何かしようとしてたことがあるのかな? そこを知りたいなって思った。
――そうか、子どもの方には、「切ってはいけない」ってないんだろね。大人には、それを教えないといけないっていう「考え」があるね。
相手の意志や気持ちに働きかける
舞子 サロンで検討してたときに、「やらせる」「やめさせる」って、本来出来ないんじゃないか、それってどういうことなのかなって考えた。
そして、相手の意志とか、気持ちに働きかけるって、本に書いてあって、それってどういうことだろう? って考えた。相手の意志に働きかけるんだったら、働きかける自分も、自分の意志とか気持ちで働きかけないと伝わらないんじゃないかな、って思った。それは、そうかもなって。
そういうことが、子どもたちが人間らしく育っていくことに関係してくるのかな…って思う。
――最近は、どんなふうに子どもと接しているの?
舞子 なんか、「やろう、やろう」ってしていた感じがあった。自分の中では、これをやりたいって、あんまり出てこなくって。
円ちゃん(チェリッシュで一緒のお母さん)からは、子どもたちと「あれやってみたいんだよね」っていう話を聞くと、私は、そういうふうに出てくるのが、「いい」みたいに思ってたのかな。
最近は、子どもたちが、「これしてほしい」とか言ったときに、自分がやろうと思ったらやるって感じかな。
あまり自分からこれしてみたいな、って出てきたらやったりするけど、無理にこれやろうって思ってた時は結構きつかった。
子どもたちが退屈しないように、集中出来る遊びを考えるとか、そういうのが「いい」って思ってた。
――子どもたちって、退屈するのかな?
舞子 どうなんだろうね?
子どもが、「面白くない」とか、「家に帰りたいとか」、そういうのを聞くと、退屈なのかなって思うんだけど。そう言った瞬間から、次の遊びが始まってたり、帰りたいっていってたのが、しばらく遊んだりとかするから、そのときそう思ったことを言ってるんだろうな。
――子どもに退屈させないように遊びを与えようとする「考え」があるよね。
舞子 集中して出来ることは、それはいいなって思うけど、そういうことが子どもの満足みたいに思ってた時期もある。だらだらして見える時でも、ただ一緒に過ごしているという時でも、いいのかなって今は思う。
――そういう時でもお母さんが安心してみてられたら、いいんだろうね。親の方が、心配しちゃって、手を出したくなったりするのかな。子どもの様子は気になるよね。
他のお母さんたちの目線があって
舞子 他の子の様子を聞いたりすると、やっぱり気になるかな。「今日はつむちゃん漢字を書いてたよ」とか、LINEで写真を送ってきたりしてね。さくとはまだその年代ではないけど。他の子をちょっと遅れてるって感じたりとか。
何か比べて、そっちの方が「いい」みたいに思ったり、同じように出来るのが「いい」って思ったり。
たつみ君とさくととは1か月ちがいで、歩くのはさくとの方が早かったんだけど。たつみ君は器用に物を入れたりしているのみると、さくとにもそういうのさせてもらえてるのかなって見たり…。さくと君は、外に出て走り回ったりするのがどうも楽しそうだよ、とか、そんなふうに見てもらってたり…。
私から見ると、たつみ君がすごく穏やかに見えるんだよね。そういうのが羨ましくなったりする、さくとは乱暴に思ったり。たつみ君はおとなしくて素直みたいに受け取ってたり。
そういう話を、知美さんとか純奈さんとか、月に1回ミーティングしてて、そういう時、話してる。
でも、「さくとすごく楽しみだよね。大きくなってくのが」って、「なんにでも関心があるし、やろうとする関心があるし」って。そういうのを聞いて、へーって思ったり。

インタビューを終えて。
子どもを見守る目線がいろいろあって、自分から見ているのと違った視点で見てくれていることが、お母さんにとっても安心なのかなと思いました。取材中、さくと君は、お母さんと一緒にいましたが、くっついたり、離れたり、部屋にあるおもちゃで遊んだり、おっぱいを飲みに来たり、満足すると、離れて、おもちゃで遊んだり、と。そんな子どもの気持ちにそって舞子さんも対応していて、それが自然に感じました。子どもの欲求って、その時々でどんどん変わっていくし、それを見てお母さんも反応してるのかな、と。
「子育て」のことを一緒に考えませんか?
アズワン鈴鹿ツアー 毎週土日で開催中!
詳しくは>>>http://as-one.main.jp/HP/tour.html
㊟1「サイエンズサロン」――人と社会の本質を探るサイエンズ研究所が主催する探究の機会。参加対象は、サイエンズ研究所会員。毎週1回2時間で6か月間行われる。人や社会の本質に通じるテーマを探究しながら日常生活への顕現を試みる。
【 続 き を 閉 じ る 】
- | -